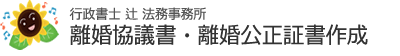離婚慰謝料が理解できるようにわかりやすく解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 離婚慰謝料のテンプレートと書き方
○ 離婚慰謝料の金額や支払方法のポイント
○ 離婚慰謝料を支払う原因(理由)は書くべき?
○ 離婚慰謝料は一括請求をしてもよい?
○ 離婚後に慰謝料請求をしても問題はない?
○ 期限の利益の喪失事項という条件の解説
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
○ 離婚慰謝料を請求できる条件と相場
○ 不倫をした配偶者への慰謝料請求の流れ
○ 不倫相手に慰謝料請求ができる条件と流れ
離婚協議書や離婚公正証書に記載する慰謝料についてお伝えします。
離婚慰謝料の書き方、テンプレートを知りたいという方が多いです。
ここでは当事務所が利用しているテンプレートを交えながら細かい点まで解説します。
![]()
離婚慰謝料のテンプレートと書き方

先ず離婚慰謝料の大事なポイントを解説する前に離婚協議書や離婚公正証書を作成する際に役立つテンプレートや書き方をお伝えします。
以下の青文字が離婚協議書や離婚公正証書に使用できる離婚慰謝料のテンプレートと書き方です。
1.慰謝料の合意
甲は、乙に慰謝料として金120万円を支払う義務があることを認め、金120万円の内金80万円は、令和7年8月10日に乙に交付した。
残り金40万円は、令和7年9月から令和8年4月まで、1か月金5万円を毎月15日までに、8回に分割して乙の口座に振込み支払う。
2.期限の利益の喪失事項
慰謝料の分割金の支払を怠れば、期限の利益を失い、慰謝料全額(既払分があれば控除する)を直ちに支払う。
離婚慰謝料の金額や支払方法のポイント
先ず協議離婚では慰謝料の金額を夫婦間の協議で決めれます。
夫婦間協議の場では支払者の支払能力を考慮した上で合意することをお勧めします。
慰謝料支払の原因が不倫の場合、感情的になり高額請求をしがちです。
ただ支払者の支払能力に見合った金額で合意しないと未払いのリスクが上がるのでご注意下さい。
つまり慰謝料請求をする場合、支払者の支払能力を計算することは大事なステップと言えます。
なお、慰謝料の相場についてはこちらのトピックにて解説しています。
次に慰謝料の支払方法について解説します。
〈代表的な慰謝料の支払方法は3つ〉
① 前払金+分割払い
② 全額を分割払い
③ 全額を一括払い
先ず上記テンプレートは①前払金+分割払いとなります。
テンプレートでは離婚前に前払金80万円を受取ることができます。
受取済みなので記載不要と考える方も多いですが、証拠として記載することが大事です。
証拠として記載することで離婚後のトラブル防止に繋がります。
例えば、乙に悪意があれば、80万円を受取っていないので払ってというウソをつけるので書く意義は十分あります。
次に夫婦間協議の結果、②慰謝料全額を分割払いで合意した場合、
離婚公正証書の効力である未払い時の強制執行(財産差押え)に備えて支払期間、分割回数、分割金額、支払日、以上4点は必ず記載して下さい。
なお、強制執行ができない離婚協議書を作成した場合でもこの4点を記載することで離婚後のトラブル防止(証拠)へと繋がります。
最後に③慰謝料全額を一括払いで合意した場合、支払時期(離婚前又は離婚後)に応じて書き方が変わります。離婚前だと証拠、離婚後だと強制執行の対象になります。ここではテンプレートを掲載していないので必要な方はお気軽にご相談下さい。
離婚慰謝料を支払う原因(理由)は書くべき?
夫婦間で慰謝料支払の合意ができて離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、支払うことになった原因(理由)を記載するべきです。(テンプレートでは文字数の関係上、省略しています。)
主な慰謝料支払の原因として不倫(不貞行為)やDVが考えられます。
なお、性格の不一致については慰謝料支払の原因にはならないのでご注意下さい。
離婚慰謝料は一括請求をしてもよい?
慰謝料を支払うベストな時期は離婚前に一括請求をして一括で受取ることです。
なぜなら一括払いだと未払いのリスクがゼロになるからです。
また専業主婦の場合、この慰謝料を離婚後の生活費に充当できるというメリットがあります。
ただ慰謝料を一括で払ってもらえるケースは稀です。
このことから現実的には分割払いで合意されるご依頼者様が多いです。
離婚後に慰謝料請求をしても問題はない?
離婚時の状況によっては離婚後に慰謝料請求をするケースもあり得ます。
例)子どもの保育園入園の関係で離婚届の提出を優先する。
このケースではデメリットがあるのでご注意下さい。
〈離婚後請求のデメリットとは?〉
・離婚後に協議を持ちかけたけど応じてくれない。
・協議が平行線で金額の妥協をせざるを得ない状況に追い込まれる。
以上のことから特別な事情がない限り、離婚前に慰謝料請求を行って合意することが望ましいです。
期限の利益の喪失事項という条件の解説
期限の利益の喪失事項を端的にお伝えすると、慰謝料の支払を怠った場合は残額を一括請求されても構わないという条件です。
期限の利益とは本来一括で支払うべき慰謝料を分割払い(分割なのでゆっくり払えるという利益を得た)にできたという意味です。
喪失事項については複数ありますが、文字数の関係上、テンプレートでは1つ(分割金の支払を怠る)だけ記載しています。
離婚公正証書に期限の利益の喪失事項の条件がない場合、強制執行時に大きな不利益が生じます。
このことから慰謝料支払の合意と期限の利益の喪失事項はセットで考えることが大事です。
![]()
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
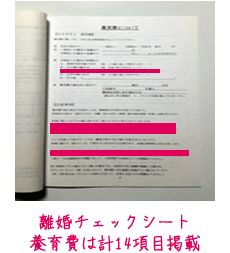
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
![]()
離婚慰謝料を請求できる条件と相場

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
どのような状況でも慰謝料の請求はできると考えている方が多いです。
この考えは間違いで離婚原因に応じて請求の可否が決まります。ここでは請求できる条件をお伝えします。
〈請求できる主な離婚原因とは?〉
① 配偶者の不倫(不貞行為)が原因
② 配偶者の暴力(DV)が原因
先ず離婚時の慰謝料請求とは婚姻中に配偶者から受けた肉体的、精神的苦痛をお金で解決することです。
上述の通り、全てのご夫婦が慰謝料請求をできる訳ではなく、離婚原因が配偶者の①不倫や②暴力の時にできるものです。
つまり離婚原因の中で1番多いと言われている性格の不一致では慰謝料請求をできないのでご注意下さい。
なお、配偶者の暴力(DV)が原因で慰謝料請求をする場合、
自分で行動するのは危険なので弁護士さんへの相談や依頼をお勧めします。
ちなみに離婚原因が不倫や暴力だったとしても、
配偶者が認めない場合、証拠がないと慰謝料請求をすることが難しいです。
例)夫が不倫を認めない状況で証拠の写真を出せと言っている。
最後に慰謝料の請求期限は離婚後原則3年という時効があります。
このことから離婚前に慰謝料の金額、支払方法などに合意してから離婚届を提出することが望ましいです。
次に慰謝料の相場についてお伝えします。
〈慰謝料相場のポイント〉
・夫婦間の協議で自由に金額を決定できる。
・支払者が現実的に支払ができる金額での合意を目指す。
協議離婚は第三者の関与を受けずに夫婦間の話し合いで進めます。
つまり不倫(不貞行為)などをされた際の慰謝料の金額は協議で自由に決めれます。
ただ自由に決めれると言っても相場を知りたい方は多いです。
相場に関するご質問をよく頂戴しますが具体的な金額をお伝えすることは難しいです。
なぜなら慰謝料の支払は分割払いになるケースが多く、支払者の支払能力という問題が大きく影響するからです。
〈支払者の支払能力とは?〉
・年収1000万円の場合、慰謝料300万円を支払うことができる。
・年収400万円の場合、慰謝料300万円を支払うのは経済的に難しい。
もちろん支払者の支払能力を無視して合意しても構わないです。
ただし、離婚後、未払いになる可能性が高いのでお勧めはできません。
以上のことから離婚協議書や離婚公正証書を作るご依頼者様の中でも不倫を原因とする慰謝料では50万円~300万円の間で合意と幅が広いです。
この幅が大きいので慰謝料の相場をお伝えすることが難しいです。
余談ですが子どもの養育費では算定表という相場がありますが、
離婚慰謝料の相場を考える場合、養育費算定表のようなものはありません。
最後に慰謝料支払の原因が不倫の場合、裏切られたという気持ちが強くなり高額請求を考えがちですが現実的な金額での合意を目指すことが望ましいです。
![]()
不倫をした配偶者への慰謝料請求の流れ

配偶者の不倫(不貞行為)が原因で離婚する場合、精神的苦痛の対価として配偶者に慰謝料請求ができます。
ここでは夫が不倫をした。という例で解説しますが、妻が不倫をしても同じ扱いです。
〈夫への慰謝料請求の流れ〉
① 夫が不倫を認める
② 慰謝料の金額を話し合う
③ 慰謝料の支払方法を話し合う
④ 話し合いで合意した条件を整理する
先ず夫に慰謝料請求をする条件として夫が不倫したという事実を認める必要があります。
仮に夫が認めない場合は証拠書類を用意しないといけません。証拠とは夫が不倫相手とホテルに入る写真などです。
次に夫が不倫を認めたら慰謝料の金額の協議を始めます。
夫の支払能力(収入と支出)をもとに計算を行い、具体的な金額を出します。
なお、支払能力をもとに計算という方法は複数ある方法の中の1つです。つまり支払能力を無視して計算するという選択肢もあります。
次に慰謝料の支払方法の協議を行います。詳細はこちらのトピックをご覧下さい。
最後に合意した条件は口約束で終えても構わないですが、
離婚後のトラブル防止のためにも証拠として書面に残すことをお勧めします。
書面とは離婚協議書や離婚公正証書のことです。
なお、離婚公正証書には証拠としての効力に加えて未払い時に強制執行(財産の差押え)ができます。
余談ですが夫に慰謝料請求をする場合、不倫相手を庇うことが多く夫婦間協議が進みやすい傾向があります。不倫相手を庇う夫を見て複雑な心情となりますが離婚に向けて割り切るという考え方も1つの手だと考えます。
![]()
不倫相手に慰謝料請求ができる条件と流れ

【目次】
○ 不倫相手に請求するための条件
○ 不倫相手への慰謝料請求の流れ
○ 不倫相手への請求は負担が大きい理由
不倫(不貞行為)の慰謝料請求は配偶者ではなく不倫相手に行うことも可能です。
〈不倫相手に請求するための条件〉
① 不倫とは性行為を指す
② 不倫相手が配偶者は既婚者だと知っていた
③ 不倫をしていたという証拠
不倫相手に慰謝料請求をする場合、①~③の条件を満たしていないと難しいです。
先ず①不倫とは性行為を指しています。食事や映画に行っただけという状況では請求できません。
次に②配偶者が不倫相手に未婚(独身)と伝えていた場合、不倫相手に請求できない可能性があるのでご注意下さい。このケースでは配偶者に請求を行います。
最後に不倫相手が不倫を認めない可能性もあります。
このことから証拠(ホテルへ出入りする写真など)を準備する必要があります。
〈不倫相手への慰謝料請求の流れ〉
① 不倫が発覚
② 不倫相手と協議する環境を整える
③ 慰謝料の金額を話し合う
④ 慰謝料の金額決定後に支払い
先ず慰謝料を受取るためには不倫相手との協議が必要です。
自分で不倫相手に連絡をして②協議ができる環境を作ることになります。
そして慰謝料の金額の合意ができれば、不倫相手からの支払を待ちます。支払を確認できたら終了です。
なお、今後のトラブル防止のために支払確認後、支払確認、第三者への口外禁止などを記載した示談書の作成が望ましいです。
〈不倫相手への請求は負担が大きい理由〉
・不倫相手に会う必要がある。
・慰謝料の金額や支払方法の交渉が必要。
自分で不倫相手に慰謝料請求をする場合、自分で連絡をして会った上で金額や支払方法の協議が必要です。
不倫相手に交渉するという行為は精神的な負担が大きいです。
さらに慰謝料を一括で受取った場合は示談書などの作成、分割払いになる場合は未払いに備えて公正証書の作成検討が必要です。1人でやることが多く負担は大きいです。
このような負担を軽減する方法は弁護士さんへの依頼です。
費用はかかりますが弁護士は代理人として相手と交渉をしてくれます。
この費用についてハードルが高いと考える方が多いので、
表現は悪いですがお金を請求しやすい配偶者へ請求する方が多いです。
当事務所では離婚協議書や離婚公正証書の作成をしていますが、
不倫相手に慰謝料請求をしたご依頼者様の多くが弁護士へ依頼をしています。
順序としては不倫相手への慰謝料請求終了後、夫婦間の離婚協議を始めるという形です。
このケースでは不倫相手から慰謝料の支払を受けているので、夫婦間の離婚協議では慰謝料の話し合いは不要となります。