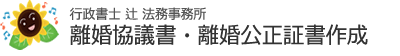面会交流の文例、書き方、ルールなどをわかりやすく解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 面会交流の文例と書き方(2つ)
○ 文例A案と文例B案の違いとは?
○ 面会交流の頻度や実施時間のポイント
○ 面会交流なし(しない)の書き方は?
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
○ 面会交流の決め方は2パターン(ルール)
○ 面会交流は何歳まで実施するべき?
○ 面会交流で決めれる細かい条件の例
○ 面会交流を養育費支払の取引に使うのはNG
○ 離婚届にある面会交流のチェック欄の意味は?
離婚に伴い離れて暮らす親と子どもとの面会交流についてお伝えします。
面会交流は子どもの成長に欠かせないものです。
夫婦間にわだかまりがあったとしても、子どもが望むのであれば実施に向けて努力することが大事です。
![]()
面会交流の文例と書き方(2つ)

先ず面会交流のルールや追加条件の詳細を解説する前に離婚協議書や離婚公正証書を作成する際に役立つ文例や書き方をお伝えします。
以下の青文字のA案とB案が面会交流の文例と書き方です。
A案
乙は、甲が1か月の内1回、長女と面会交流することを認め、面会交流の日時や場所については面会交流の都度、協議の上決定する。
B案
甲及び乙は、甲と長女の面会交流について、1か月の内1回、毎月第1日曜日の午前9時から午後3時まで、実施することで合意した。
文例A案と文例B案の違いとは?
面会交流のルール(頻度や条件)は夫婦間の協議で自由に決めれます。
ただ離婚時の状況、環境、離婚原因に応じて内容が大きく変わりやすいです。
甲(主に父親)と子どもの交流に問題(抵抗感)がない場合、
A案のように頻度のみ定めて、他の条件は都度協議(抽象的)と取り決めて柔軟に実施します。
一方、甲と子どもの交流に問題(抵抗感)がある場合、
B案のようにルール(頻度、実施日、実施時間)を細かく取り決めて強い縛りをつけて実施します。
ご夫婦ごとに強い縛りの度合いは異なりなります。
つまり状況に応じて待合せ場所、親権者同伴などの条件を追加することもあります。
当事務所ではB案の状況だと10個以上のルールを取り決めるご依頼者様が多いです。
面会交流の頻度や実施時間のポイント
先ず面会交流の頻度は夫婦間協議で決めれますが、
子どもの気持ち、子どもの成長のため。という視点を忘れないで下さい。
次にA案では甲と子どもの交流に問題がないので頻度ではなく、
甲又は子どもが望んだ時に実施。という抽象度の高い取り決めもできます。つまり面会交流は自由という意味です。
そして面会交流の実施時間はお子様の年齢に左右されるケースが多く、正解をお伝えすることが難しいです。
当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
子どもが幼いという理由で朝食後からスタートして夕食前に終了というケースが多いです。
なお、お子様が幼い場合、親権者が同伴しているケースが多いです。
面会交流なし(しない)の書き方は?
夫婦間協議の結果、面会交流はなしという合意をされる方もいらっしゃいます。
この条件は子どもの会いたいという気持ち(希望)を無視していることが多く、問題のある合意だと考えられます。
問題のある合意については離婚協議書や離婚公正証書に記載(残す)することはできないです。
仮に面仮交流はなしという合意をされている場合、代替案を検討する必要があるため専門家などへの相談をお勧めします。
子どもの気持ちを大事にする
面会交流は子どもの気持ちを最優先に考えて実施するべきものです。
離婚原因によっては会わせたくないと考えることもありますが、
子どもが拒否しない限り、子どもの希望、気持ちを叶えることが大事です。
![]()
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
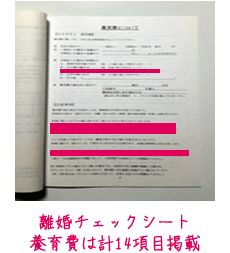
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
![]()
面会交流の決め方は2パターン(ルール)

協議離婚は夫婦間の話し合いで進めることができます。
つまり面会交流の頻度などの条件は自由に決めることができます。
注)自由だとしても法的に無効な条件は決めれません。
〈面会交流の決め方の方向性は2つ〉
① 条件を細かく決めない(抽象的)
② 条件を細かく決めていく(具体的)
上述の通り、離婚時の状況、環境、離婚原因に応じて面会交流の決め方は変わります。
子どもが自分の気持ちや希望をハッキリと言える年齢の場合、
以下の例1のように頻度を決めずに子どもの気持ちを尊重した方がよいと考えられます。
例1 子どもが望んだ時に面会交流を実施する。
つまり①細かく決めない(抽象的)方がよいということです。
当事務所では子どもが中学生以上の場合、例1のように決めるご依頼者様が多いです。
また離婚の時点で子どもが幼い場合でも親権者(主に母親)に抵抗感がなければ、例1のように決めることもあります。
なぜなら細かく決めすぎると面会交流の実施が硬直化するためです。
硬直化とは想定外の事態が起きた場合、対応が難しくなる(がんじがらめ)ことです。
一方、離婚後の居住地(遠距離)や離婚原因を考慮した結果、
以下の例2のように細かく決めて面会交流を実施した方がよいケースもあります。
例2 毎月第1日曜日の午前中に○○公園で実施する。
離れて暮らす親(主に父親)と親権者の関係が良好でない場合、
例2のように頻度や条件について②細かく決める(具体的)ご依頼者様が多いです。
なお、例2は頻度、日時、面会場所を決めていますが、
夫婦間協議の結果、代替日の決定や交流時の費用負担などを追加で決めることもあります。
最終的に10個以上の条件で合意するご依頼者様も多いです。
もちろん例1でお伝えした硬直化というリスクを理解した上での結論です。
どちらの決め方(ルール)を選択しても問題はありません。
ただし、双方が子どもの気持ち、希望が最優先という視点を持って協議することが大事です。
面会交流は何歳まで実施するべき?
何歳までという具体的な年齢をお伝えするのは難しいです。
なぜなら子どもが自分の気持ち、希望を主張できる年齢(精神年齢)に差があるためです。
ただ子どもが高校生の場合は決めなくてもよいと考えるご依頼者様は多いです。
つまりこのケースでは夫婦間で条件協議を行わずに子どもの希望に任せるということです。
![]()
面会交流で決めれる細かい条件の例

基本的な面会交流の条件(A案やB案)だけ決めても構わないですが、
当事務所では離婚後のトラブルを防ぐために細かい条件を追加で決めるご依頼者様が多いです。
具体的な細かい条件の一部を以下にてお伝えします。
離婚チェックシートには面会交流の13個の追加条件を全て掲載しています。
〈細かい条件の例〉
① 夏休みなどの交流
② 誕生日などのイベントへの参加
③ 交通費などの費用負担
④ 交流中に他方の悪口を言わない
⑤ 親権者の同伴
先ず面会交流の追加条件の内①と②については、
その言葉通りの意味になるので詳しい解説は割愛させて頂きます。
次に③費用負担の条件については9割以上のご依頼者様が合意をしています。
特に離婚後の居住地が遠距離になる場合、この条件を話し合うことは大事です。
例)離れて暮らす親が東京、子どもは大阪で過ごしている。
次に離婚した時の夫婦間の感情や状況にもよりますが、
最近は④悪口を言わないという条件の合意をするご依頼者様が増えています。
例)お母さんのせいで離れて暮らすことになったというウソを子どもに伝える。
そして子どもが幼い時に離婚することになった場合、
付き添いが必要と考えて⑤親権者の同伴を条件にするご依頼者様も多いです。
なお、付き添いについては子どもの成長に伴い解除するという解除条件もセットで記載します。
![]()
面会交流を養育費支払の取引に使うのはNG

面会交流は親権や養育費とセットで協議するべきです。
ただ面会交流の条件協議の際、養育費支払の取引材料として使うのは問題があります。
〈よくある取引の事例とは?〉
・養育費はいらないから交流もさせない。
・交流を希望しない代わりに養育費を払わない。
離婚原因によってはこのような条件合意をするケースもありますが、
面会交流は子どもの気持ちを優先するべきなので養育費支払とは切り離して考えます。
子どもが拒否している場合を除いて、できる限り実現する努力をして下さい。
また離婚後、養育費の支払状況が悪い(未払い)場合、
以下のようなケースが起きやすいですが、この状況でも養育費支払とは切り離して考えます。
元妻「養育費を払ってくれるまで面会交流は中断します。」
上述の通り、面会交流は子どもの気持ちが最優先されます。
つまり離婚後にこのようなケースが起きても面会交流を取引材料にするのはNGです。
つまり面会交流と養育費はどちらも夫婦間で協議するべきですが、支払状況は別の話となります。
離婚届にある面会交流のチェック欄の意味は?
〈離婚届のチェック欄〉
・面会交流の取決めをしている。
・面会交流をまだ決めていない。
離婚届の右下に面会交流のチェック欄があります。
これには法的拘束力はなく子どもに対する意識向上を目的としています。
仮に決めていないにチェックを入れても離婚届が受理されないという訳ではありません。
つまりどちらにチェックを入れても役所の提出時に問題は起きません。
ただし、離婚後の新生活でつまずかないためにも、
離婚前に夫婦間で面会交流の条件協議を行うことをお勧めします。
例)何も決めずに離婚したので、離婚後、面会交流の頻度で揉める。
なお、離婚届には養育費のチェック欄もあります。これも面会交流と同じで子どもに対する意識向上を目的としています。