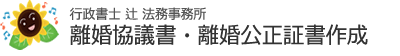年金分割が理解できるようわかりやすく解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 年金分割合意書の文例と書き方
○ 文例と書き方のポイント解説
○ 年金分割合意書はどのような書類?
○ 合意分割の按分割合と年金分割改定者とは?
○ 年金分割合意書と公正証書の関係とは?
○ 年金分割しないという書き方は?
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
○ 年金分割制度を端的にまとめると
○ 年金分割の手続方法は3パターン
○ 3号分割の特徴や手続きを端的にまとめると
○ 合意分割の特徴や手続きを端的にまとめると
離婚時の年金分割制度をわかりやすくお伝えします。
年金分割は馴染みがなく難しい言葉が多いので難しいと感じる方が多いです。
ここではできる限り噛み砕いた表現を利用していますが、わかりにくい場合はお気軽にご相談下さい。
![]()
年金分割合意書の文例と書き方

先ず年金分割の特徴や手続き方法の詳細を解説する前に離婚公正証書や年金分割合意書を作成する際に役立つ文例や書き方をお伝えします。
以下の青文字が年金分割合意書の文例と書き方です。
甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法第78条の2の規定により、日本年金機構理事長に対し、対象期間(婚姻期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0、5とすることに合意した。
文例と書き方のポイント解説
青文字の文例は難しい言葉で埋め尽くされています。
ただ夫婦間協議で決める按分割合(文例では0、5)以外は丸写しで問題ありません。
一般的には折半(50%)が妥当だと考えられます。
このことから按分割合は0、5(50%)で合意されるご夫婦が多いです。
なお、年金分割の請求期限は離婚後2年以内(時効)です。忘れないように早めに手続きをして下さい。
ちなみにここで公開している文例は離婚前用の文例です。離婚後に作成する場合は文例の内容が変わるのでご注意下さい。
ここでは年金分割の制度や手続き方法についてお伝えしていますが、
正直な話、文字(HP)だと上手く解説することが難しいと感じています。
よくわからない。という方は無料の電話相談をご利用下さい。
年金分割合意書はどのような書類?
先ず年金分割には3号分割と合意分割、以上2つの手続方法があります。
離婚後、何か事情があり1人で合意分割の手続き(請求)を行いたい場合、
事前に公証役場で年金分割合意書を作成し年金事務所に提出する必要があります。
〈どのような事情?〉
・元夫が仕事を休めなくて年金事務所に行けない。
・離婚後の居住地が遠いため、年金事務所に行くことが難しい。
逆に離婚後に元ご夫婦が揃って年金事務所に出向ける場合、この合意書を作る必要はありません。
なお、合意分割ではなく3号分割に該当するご夫婦の場合、
年金分割合意書は不要なので、何も作らずに離婚後1人で年金事務所で手続きができます。
合意分割の按分割合と年金分割改定者とは?
先ず合意分割の按分割合は夫婦間の協議で自由に決めることができます。
按分割合の範囲の最大値は折半(50%)ですが最小値はご夫婦ごとによって異なるので事前に調べる必要があります。
按分割合の範囲を知るためには年金事務所にて年金分割のための情報通知書の請求が必要です。
なお、3号分割の按分割合は一律折半と決まっています。つまり夫婦間での協議は不要です。
そして年金分割の改定者とは手続きを行うことで減る人、増える人を指すものです。
年金分割で減る人を第1号改定者、増える人を第2号改定者と言います。主に第1号は夫、第2号は妻になるケースが多いです。
上述した年金分割のための情報通知書を取得できれば、
婚姻期間の年金情報、改定者の情報、按分割合の範囲などを知ることができます。
合意分割の手続きを考えた場合、この情報通知書の請求から始めて下さい。
年金分割合意書と公正証書の関係とは?
合意分割の夫婦間協議で決めた按分割合を書面に残す場合、
年金分割合意書、又は公正証書いずれかの書面を公証役場にて作成します。
注)どちらの書面も公証役場でしか作成できません。
文例はどちらも同じ内容ですが作り方や費用に違いがあります。
詳しい解説は差し控えますが、費用が安い年金分割合意書の作成をお勧めします。
年金分割しないという書き方は?
夫婦間協議の結果、年金分割(厳密には合意分割)をしないという合意をされる方もいらっしゃいます。
この条件を離婚公正証書に記載できる、できないの判断は公証役場の公証人ごとにわかれる可能性があります。
このことから作成予定の公証役場にて記載可否確認を行い、記載可となれば専門家などに書き方の相談をお勧めします。
![]()
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
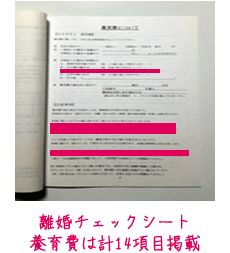
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
![]()
年金分割制度を端的にまとめると

先ず全てのご夫婦が年金分割の手続きをできる訳ではありません。
自分が対象者として該当する、しないの確認を始めることがスタートラインです。
年金分割の制度とは?
① 婚姻期間中に納付した
② 厚生年金が年金分割の対象になる
離婚時の年金分割は婚姻中にご夫婦の一方(双方)が納付した厚生年金の一部を他方配偶者に分割(移す)することです。
年金分割は妻の権利と思われがちですが、婚姻中の働き方(共働き、専業主夫)に応じて妻が納付した厚生年金の一部を夫に分割するケースもあり得ます。
なお、共働きのご夫婦は経済的に自立しているため年金分割をしないという結論を出すご依頼者様もいます。
婚姻中に国民年金しか納付していない場合は?
婚姻中に国民年金しか納付していないご夫婦(主に自営業者)の場合、年金分割の対象者から外れます。
つまり年金分割の手続きはできないので夫婦間で協議する必要はありません。養育費などその他の離婚条件の協議を行います。
年金分割の手続方法は3パターン
① 3号分割の請求を行う
② 合意分割の請求を行う
③ 3号と合意(併用)の請求を行う
年金分割の手続方法は3パターン(①~③)あります。
これはご夫婦が自由に選べるものではなく、婚姻日や婚姻中に働き方に応じて決まります。
つまり自分がどの方法に該当するのかという判断を間違えると、
時間の無駄になったり、やり直しの可能性があるため判断が難しい場合は専門家への相談をお勧めします。
具体的な手続方法は次のトピックで解説していきます。
![]()
3号分割の特徴や手続きを端的にまとめると

【目次】
○ 3号分割の特徴は4つ
○ 共働きの夫婦は3号分割の該当者になる?
○ 3号分割の手続き事例1
○ 3号分割の手続き事例2
3号分割の制度はわかりやすくて手続きをしやすいという特徴があります。
〈3号分割の特徴は4つ〉
① 平成20年4月以降に納付した厚生年金が対象。
② 婚姻中に専業主婦(主夫)又は扶養内の仕事をしていた方が対象。
③ 配偶者との按分割合の協議は不要。
④ 離婚後、2年以内に手続きをすれば折半(50%)で分割。
3号分割の対象者は③配偶者との按分割合の協議は不要です。
また④離婚後、1人で年金事務所に出向いて手続きをすれば折半で分割されます。
さらに年金分割のための情報通知書の請求や年金分割合意書の作成も不要です。
ただし、①と②の条件クリアが必要なので誰もが利用できる制度ではありません。
なお、配偶者に内緒で3号分割の請求をしても構わないですが、
離婚後に配偶者が請求の事実を知るとトラブルになる可能性があるので離婚前に制度説明をすることが大事です。
共働きの夫婦は3号分割の該当者になる?
共働きのご夫婦は双方が扶養外の仕事で厚生年金を納めています。
つまり②の条件をクリアできないので次のトピックの合意分割の対象者となります。
基本的に3号分割の対象から外れる場合は合意分割になると考えるとわかりやすいです。
3号分割の手続き事例1
・平成20年5月に婚姻
・令和7年8月に離婚
・夫は会社員で厚生年金を納付
・妻は専業主婦や扶養内パートの期間があり
先ず夫が会社員で厚生年金を納付しています。
つまり年金分割の対象となり手続方法を検討する必要があります。
次に婚姻日が平成20年4月以降で妻は夫の扶養に入っていたので、
3号分割の特徴①と②の条件をクリアをしているため、離婚後、妻が1人で年金事務所に請求できます。
最後に妻が3号分割の請求をすれば折半(50%)で分割されます。
3号分割の手続き事例2
・平成15年6月に婚姻
・令和7年8月に離婚
・夫は公務員で厚生年金を納付
・妻は専業主婦や扶養内パートの期間があり
婚姻日が平成20年4月より前で妻は夫の扶養に入っていたので、
婚姻~平成20年3月までは合意分割、それ以降は3号分割の該当者となります。
つまり合意分割の期間は夫婦間で按分割合の協議が必要です。
一方、3号分割の期間は夫婦間協議が不要で2つの手続きの該当者という併用請求になります。
この併用請求があるため年金分割の手続きが難しいと感じる方が多いです。
最後に3号分割の手続きはわかりやすいですが婚姻日や婚姻中に働き方に左右されるので請求できる人が少ないという特徴があります。
![]()
合意分割の特徴や手続きを端的にまとめると

【目次】
○ 合意分割の特徴は4つ
○ 合意分割の手続き事例1
○ 合意分割の手続き事例2
合意分割の制度は3号分割と比較するとわかりにくいため難易度が一気に上がります。
〈合意分割の特徴は4つ〉
① 婚姻~平成20年3月までに納付した厚生年金が対象。
② 夫婦間の協議で按分割合を決定する。
③ 按分割合の範囲を知るために情報通知書が必要。
④ 離婚後、元夫婦が揃って手続きを行う必要がある。
※ ①に関しては例外があります。詳細はこちらです。
先ず合意分割は②配偶者との協議が必要です。
按分割合の合意ができない場合、年金分割の請求はできないです。
これは按分割合が折半(50%)と決まっている3号分割との違いです。
つまり夫婦間協議が不要な3号分割と比較すると手間がかかる制度と言えます。
次にご夫婦ごとに③按分割合の範囲が異なるため、
事前に年金事務所に年金分割のための情報通知書の請求が必要となります。
按分割合の最大値は50%ですが最小値はご夫婦ごとにことなります。
例)按分割合の範囲は「○%越え、50%以下」と記載されています。
なお、離婚後、対象者が1人で請求をしたいと考えている場合、
事前に公証役場で年金分割合意書、又は公正証書を作る必要があります。
注)離婚後、2年以内であれば離婚後に作ることも可能です。
最後に夫婦間協議で按分割合の合意ができない場合、
年金分割の請求を諦める、又は家庭裁判所の調停で解決を目指します。
合意分割の手続き事例1
・平成20年1月に婚姻
・令和7年8月に離婚
・夫は会社員で厚生年金を納付
・妻は会社員で厚生年金を納付
先ず夫と妻双方が会社員で厚生年金を納付しています。
つまり年金分割の対象となり手続方法を検討する必要があります。
次に夫妻は平成20年1月に婚姻しているので、
合意分割の特徴①に該当しているため、按分割合の協議が必要となります。
ここで1つ疑問を持つ方がいるかもしれません。
それは平成20年4月以降に納付した厚生年金はどうなる?という点です。
扶養外の仕事をしている共働きのご夫婦は3号分割から外れます。
このケースでは平成20年4月以降も合意分割に該当します。つまり婚姻期間全てが合意分割となります。これが合意分割の特徴①の例外です。
次に合意分割の按分割合の範囲を知る必要があります。
これは年金事務所で年金分割のための情報通知書を請求すれば把握できます。
最後に按分割合の合意をして離婚後、元夫婦が揃って年金事務所にて請求をすれば手続きは終了となります。
合意分割の手続き事例2
・平成22年1月に婚姻
・令和7年8月に離婚
・夫は会社員で厚生年金を納付
・妻は会社員で厚生年金を納付
・婚姻中、妻は4年間の専業主婦の期間がある
先ず婚姻日が平成20年4月以降で妻は会社員と専業主婦の期間があります。
このケースでは会社員の期間は合意分割、専業主婦の期間は3号分割という併用請求となります。
この会社員や専業主婦の期間で手続方法が変わるため、
年金分割(特に合意分割)の手続きはややこしくて難しいと感じる方が多いです。
婚姻期間が短いご夫婦の場合、併用請求に該当するケースが多いです。
例)妻は婚姻から1年後に会社を辞めて専業主婦になった。
また将来的にこのケースに該当するご夫婦は少しずつ増えると予想されます。
例)妻は子の小学校入学をきっかけに専業主婦から扶養外パートを始めた。
以上で年金分割に関する解説を終えます。
上述の通り、難しいという方はお気軽に無料の電話相談をご利用下さい。