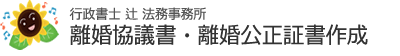協議離婚が理解できるようわかりやすく解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 協議離婚の合意に関する文例と書き方
○ 文例と書き方のポイント解説
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
○ 協議離婚の進め方と流れ(離婚スケジュール)
○ 効率の良い離婚の話し合いの進め方
○ 協議離婚成立までの期間の平均や費用は?
○ 離婚前に知っておきたい協議離婚のトラブル集
○ 離婚届と離婚後の手続きのポイント解説
離婚協議書や離婚公正証書に記載する協議離婚の合意についてお伝えします。
さらに協議離婚のスケジュール(進め方や流れ)、成立までの期間などについても当事務所の経験をもとに具体例を交えながら解説します。
![]()
協議離婚の合意に関する文例と書き方

先ず協議離婚の大事なポイントを解説する前に離婚協議書や離婚公正証書を作成する際に役立つ文例や書き方をお伝えします。
以下の青文字が協議離婚の合意に関する文例と書き方です。
甲(夫)及び乙(妻)は、本離婚協議書をもとに離婚給付等に関する契約公正証書を作成した後、離婚届を提出する。
文例と書き方のポイント解説
先ず離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合の夫と妻の表記は「甲と乙」を使います。
また子どもは「丙や丁」を使いますが、当事務所ではわかりやすいように「長男や長女」という表記を使っています。
なお、氏名は離婚の前後で表記が変わるのでご注意下さい。
離婚前に作成する場合は婚姻中の氏、離婚後に作成する場合は離婚後の氏となります。
次に文例の「離婚給付等~公正証書」については離婚公正証書作成時に必要なもので離婚協議書では不要です。
離婚協議書と離婚公正証書の文例や書き方は一部を除いてほぼ同じ内容となります。
最後に文例の「離婚届を提出」についてはご夫婦の判断で入れる、入れないを決めれます。当事務所のご依頼者様は100%入れています。
なお、離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、完成後に離婚届を提出しないと効力が発生しないのでご注意下さい。
つまり離婚協議書や離婚公正証書が完成したら迅速に離婚届を提出することが大事です。
![]()
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
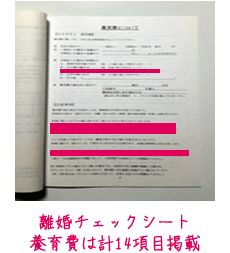
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
![]()
協議離婚の進め方と流れ(離婚スケジュール)

先ず協議離婚は調停離婚や裁判離婚とは異なって裁判所の関与を受けることなく夫婦間の協議で進めることができます。
つまり協議離婚の進め方や流れはご夫婦の自由な意思で決めれます。
参考情報として当事務所のご依頼者様の進め方は以下の通りです。これから離婚する方にとって参考になると思います。
〈具体的な進め方と流れとは?〉
① 夫婦双方が離婚したいと考える
② 養育費など離婚条件の話し合いを開始
③ 全ての離婚条件に合意する
④ 離婚協議書や離婚公正証書を作成する
⑤ 離婚届を提出して協議離婚成立
⑥ 離婚後の手続きを始める
先ず協議離婚の成立条件は離婚するという意思、未成年の子どもの親権者の決定、離婚届の提出、以上3つだけです。3つだけなのでシンプルでわかりやすいです。
次に③全ての離婚条件とは親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などを言いますが、協議離婚の成立条件で求められているのは親権者の決定だけです。
つまり未成年の子どもがいる場合は親権の協議は必要ですが、養育費など他の離婚条件は任意(協議するのは自由)となります。
ただ夫婦間で親権以外の離婚条件の協議をしないと決めた場合、離婚後、以下のようなトラブルが起きる可能性があります。ご注意下さい。
〈どのようなトラブル?〉
元妻「物価が上がって大変だから養育費を払ってほしい。」
元夫「今になって言われても困る。自分にも生活があるから。」
この養育費トラブルは離婚時に協議をしていれば防げたものです。
このことから任意だと言っても離婚前に親権以外の条件も協議することが望ましいです。
なお、④離婚協議書や離婚公正証書の作成も任意です。
夫婦間協議の結果、作らないという選択をすることも可能です。
ただこのケースでは夫婦間で合意した離婚条件は口約束で終えることになります。
効率の良い離婚の話し合いの進め方
効率良く離婚協議を進める方法は二度手間を避けることです。
協議離婚では養育費などの離婚条件を夫婦間の話し合いで進めます。
この離婚協議の場では以下のような二度手間、三度手間が起きるケースが多いです。
〈二度手間の状況とは?〉
夫「養育費は月3万円で20歳まで支払うね。」
妻「昨日、友達から20歳ではなく4大卒の方がよいと言われた。」
〈三度手間の状況とは?〉
夫「わかった。終期は4大卒でいいよ。」
妻「4大卒でいいなら浪人した場合のことも決めたい。」
このような二度(三度)手間が起きる原因は、離婚協議前に行う情報収集が不十分だからです。
不十分な状態で離婚協議を始めた場合、新しい情報が入るたびに再協議が行われます。つまり効率が悪いです。
以上のことから協議離婚の話し合いでは事前準備として正確な情報や知識を集めることが大事です。
なお、正確な情報や知識はウェブサイト、書籍、離婚経験者、専門家などから集めることができます。当事務所では離婚チェックシートを利用するので情報収集は不要です。
![]()
協議離婚成立までの期間の平均や費用は?

先ず協議離婚が成立するまでの期間はご夫婦ごとに異なります。
なぜなら婚姻期間、子どもの有無などによって夫婦間で話し合う離婚条件の種類が異なるからです。
当事務所のご依頼者様の場合、上述した具体的な進め方と流れ通り進めた場合、期間は平均1か月~2か月程度になることが多いです。
なお、協議離婚では夫婦間で納得できるまで離婚条件を話し尽くすことが大事です。話し尽くすことで離婚後の後悔やトラブル率が下がります。
このことから夫婦間協議が長引いて1年以上かかるご依頼者様も少数ですががいらっしゃいます。
〈夫婦間協議が長引くケースとは?〉
・子どもの養育費の支払額について隔たりがある。
・不動産の財産分与で住宅ローン問題を抱えている。
特に住宅ローン問題は銀行の関与を受けるため夫婦間で解決することが難しく長引きやすいです。ただ他の選択肢を模索するなど諦めないことが大事です。
なお、協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものです。
このことから夫婦間の離婚協議では100対0という結果は出にくいです。
離婚協議の前に譲れる離婚条件、譲れない離婚条件を整理しておくことも大事です。
次に協議離婚でかかる費用をお伝えします。
〈協議離婚にかかる費用とは?〉
・原則、費用はかからない
・離婚条件を書面に残す場合は費用がかかる
先ず協議離婚の進め方は夫婦間の話し合いがベースになるので第三者の関与を受けません。つまり費用はかからないです。
また離婚届も役所で無料配布されているので費用はかかりません。
以上のことから協議離婚の場合、原則、費用はかかりません。
ただし、夫婦間で協議した養育費などの離婚条件を口約束ではなく書面(離婚協議書や離婚公正証書)に残す場合は費用がかかるケースがあります。
ご夫婦(自分たち)で離婚協議書を作成する場合、費用はほぼ0円(用紙代やインク代程度)ですが、行政書士などの専門家に依頼をした場合は費用(報酬)がかかります。
一方、離婚公正証書は公証役場でしか完成できず、必ず公証役場手数料の支払が必要なので費用はかかります。
離婚協議書と離婚公正証書の詳細は以下をご覧下さい。
・サンプル通りに作っても大丈夫?|離婚協議書と離婚公正証書作成
こういう訳で協議離婚では基本的に費用はかかりませんが、夫婦間で合意した条件を書面に残す場合は費用がかかることがあります。
![]()
離婚前に知っておきたい協議離婚のトラブル集

ここでは協議離婚のトラブル例を3つご紹介します。
離婚することで夫と妻は夫婦から他人となり、それぞれが新しい気持ちで新生活を始めます。
この新生活でつまずかないために役立つトラブル集なので是非ご覧下さい。
【目次】
○ 離婚したい気持ちが強すぎて・・・
○ お金はあるのに養育費を払ってくれない
○ 離婚協議書に書いた面会交流の約束を破られる
離婚したい気持ちが強すぎて・・・
離婚原因によっては配偶者の顔を見るのが嫌になって早く別れたいという思いから急いで離婚届を提出することがあります。
離婚原因が配偶者の不倫(不貞行為)の場合、このような気持ちになりやすいです。
協議離婚の成立条件には親権以外の離婚条件は含まれないので、
離婚後に落ち着いてから話し合いをしようという約束をするご夫婦もいらっしゃいます。
その結果、離婚後に話し合いを求めても元配偶者の反応が鈍くて、養育費などの協議が進まないというトラブルが起きやすくなります。
協議離婚で話し合う期間は離婚後の人生に比べると短いです。
急ぎたい気持ちも理解できますが後悔しないためにも離婚前に協議することが大事です。
離婚後に協議を行うのはお勧めできないという協議離婚の進め方です。
お金はあるのに養育費を払ってくれない
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指します。
つまり養育費の条件(金額や支払日など)も自由に決めることができます。
そして夫婦間で合意した条件を口約束で終えた場合、
離婚後にこのような未払問題が起きる可能性は十分考えられます。
現在、未払いを100%防ぐ方法はありません。
ただ合意した条件を書面に残した場合、口約束より支払率を上げることができます。
書面とは離婚協議書や離婚公正証書のことです。
特に離婚公正証書には強制執行(未払い時の差押え)という強い効力があります。
協議離婚は自由度が高い代わりに自己責任が生じます。
離婚後に自己責任を感じて後悔する場面を減らす準備をすることは大事です。
離婚条件を口約束で終えるというお勧めできない協議離婚の進め方です。
離婚協議書に書いた面会交流の約束を破られる
離婚協議書には夫婦間で合意した離婚条件が記載されます。
ただご夫婦(自分たち)で作成した場合、無効な条件合意を書いているケースがあります。
〈無効な条件の例〉
・離婚後、面会交流は一切実施しない。
・養育費を払わない場合は面会交流を実施しない。
無効な条件合意は何も決まっていない状態と同じです。
つまり元配偶者が無効と知った場合、トラブルに発展する可能性があります。
このトラブルを防ぐ方法は1つだけあります。
それは夫婦間で離婚協議を行う前に正確な離婚情報を集めることです。
正確な情報や知識があれば無効な条件合意を交わすことはありません。
なお、離婚公正証書は公証役場の公証人が完成させます。
事前に公証人のチェックを受けるので無効な条件合意が記載されることはありません。
最後に面会交流は子どもの成長に欠かせないものです。
夫婦間でわだかまりがあったとしても実現させることが大事です。
準備不足で離婚協議を始めるというお勧めできない協議離婚の進め方です。
![]()
離婚届と離婚後の手続きのポイント解説

夫婦間で離婚条件の協議を終えた後、役所に離婚届を提出すれば協議離婚は成立となります。
〈離婚届のポイント〉
・証人は2人必要
・養育費と面会交流のチェック欄
先ず離婚届を完成させるためには証人が2人必要です。
この証人の条件は成人であることです。
一般的に身近な人(親族や友人など)にお願いをするご夫婦が多いです。
ご依頼者様からお話があった場合、私が離婚届の証人になることもあります。
証人になってくれる人がいない、身近に頼める人がいないという場合は証人代行サービスの利用を検討して下さい。
当事務所でも離婚届の証人代行サービスを行っています。
詳細は別サイトになりますが、下記をご覧下さい。
・料金は安心の後払い‐全国対応の離婚届証人代行サービス
次に離婚届の右下にある養育費と面会交流のチェック欄についてお伝えします。
このチェック欄には法的拘束力がなく夫婦間の意識向上を目的としています。
仮に「決めていない」にチェックを入れても何か問題が起きる訳ではありません。
つまり離婚届は受理されるので協議離婚は成立します。
離婚届を提出すれば法律上は協議離婚が成立します。
ただ離婚後にしかできない手続きもあるので、離婚前から準備することをお勧めします。
〈離婚後の手続き(一例)〉
・運転免許証やマイナンバーカードなどの名義変更
・年金分割(合意分割や3号分割)の申請
・児童扶養手当や児童手当の申請
・子どもの氏の変更許可申立
先ず各窓口では本人確認書類の提示を求められることが多いです。
効率良く進めるためにも運転免許証やマイナンバーカードの変更手続きから始めることをお勧めします。
次に年金分割の申請方法は3パターンあり複雑です。
離婚前から申請の準備(特に合意分割)をしておくことが望ましいです。
年金分割の詳細は下記をご覧下さい。
・年金分割合意書の書式|文例や公正証書との関係も解説
次に児童扶養手当などの公的扶助は生活費の足しになります。
離婚前から役所に相談をしてスムーズに申請できるように準備をして下さい。
最後に離婚後の子どもの氏と戸籍についてお伝えします。
離婚成立後、親権者と子どもの戸籍は別々になるケースが多いです。
子どもを従前の戸籍から抜いて、親権者の新戸籍に入れる手続きが必要です。
例)子どもを婚姻時の父親の戸籍から抜いて母親の新戸籍に入れる。
この手続きは2つの申請が必要となります。
1つ目は家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立を行います。
2つ目は役所に入籍届を提出します。これで子どもの氏と戸籍の手続きは完了です。
なお、離婚後の手続きリストといった冊子を置いている役所もあります。1度ご確認下さい。
以上のことから離婚後の手続きはたくさんあります。
これらを終えて始めて本当の意味での協議離婚の成立(終了)と言えます。