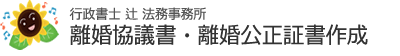財産分与が理解できるようわかりやすく解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 財産分与の文例と書き方(不動産・預貯金・動産)
○ 自分に合う不動産の書き方が見つからない方へ
○ 文例と書き方のポイント解説
○ 財産分与を端的にまとめると
○ 財産分与の分配割合はどうなる?
○ 子ども名義の財産の注意点
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
○ 住宅ローンを完済しているご夫婦の選択肢は2つ
○ 住宅ローンを返済中のご夫婦の選択肢は3つ
○ 不動産の名義を夫から妻に変更できる?
○ 共有名義やペアローン(連帯債務)の場合は?
○ 家具家電など動産の財産分与が大事な理由
○ 理想的な財産分与の分配協議の進め方
○ 財産分与の相場のポイントは3つ
離婚協議書や離婚公正証書に記載する不動産、預貯金、動産の財産分与の書き方を解説します。
さらに理想的な財産分与協議の進め方などこれから財産分与の話し合いを始める方に役立つ情報もお伝えします。
![]()
財産分与の文例と書き方(不動産・預貯金・動産)

先ず財産分与の大事なポイントを解説する前に離婚協議書や離婚公正証書を作成する際に役立つ文例や書き方をお伝えします。
以下の青文字が財産分与に関する文例と書き方です。
1.不動産(家やマンション)の財産分与
甲及び乙は、財産分与として令和7年8月1日に甲単独名義の不動産を甲が全て取得することで合意した。(不動産情報の記載は省略)
2.預貯金の財産分与
甲及び乙は、財産分与として令和7年8月1日に預貯金金500万円の内、甲が金50万円、乙が金450万円受領した。
3.動産の財産分与
甲及び乙は、財産分与として令和7年8月5日に甲は、テレビと冷蔵庫を取得し、乙は、エアコンとパソコンを取得した。(家電の製品情報の記載は省略)
自分に合う不動産の書き方が見つからない方へ
不動産の財産分与は夫婦間の協議で自由に決めれます。
ただし、住宅ローンが残っている場合は銀行の制約を受けるため自由に決めれないケースがあります。
このことから不動産の財産分与ではご夫婦ごとに結論が変わるので文例や書き方も数多くあります。
〈不動産の財産分与の結論(一例)〉
・夫名義の不動産を夫が取得する。(上記文例)
・夫名義の不動産を妻名義にする。
・夫婦共有名義の不動産の夫の持分を妻に渡す。
・不動産の名義変更に伴い妻が住宅ローンの借換を行う。
・離婚後、不動産を売却し売却益を分配する。
・離婚後、不動産を売却し売却損を負担する。
このように不動産の財産分与は複雑なケース(不動産の話+住宅ローンの話など)が多く難易度も高いので離婚協議書や離婚公正証書の文例や書き方が見つからない方は専門家への相談や依頼をお勧めします。
文例と書き方のポイント解説
財産分与には養育費のように金銭支払の条件もありますが、
基本的には財産を清算したという証拠の合意が多数を占めます。
この証拠の合意は離婚後のトラブル防止に役立つので、
文例1~3のように証拠の日付を記載することが望ましいです。
この日付は合意日になります。つまり全て同じ日付になるとは限りません。
〈離婚後のトラブル例〉
・預貯金の分配は折半で合意したのに7対3だとウソの再請求をされる。
・テレビはもらっていいと言われたのにやっぱり返してと再請求される。
なお、離婚協議書などに清算条項という条件を入れるとこのトラブル(離婚後の再請求)は防げます。
清算条項の詳細は以下をご覧下さい。
・清算条項の書き方と例文|離婚協議書と離婚公正証書作成
財産分与を端的にまとめると
財産分与は婚姻中に蓄えた財産を清算(分配)することです。
主に不動産、預貯金、動産(家財道具)、以上3つに分類されます。
財産分与では婚姻中に蓄えた財産が対象になります。
つまり独身時代に蓄えた財産や相続で得た財産は対象外(分配不要)となります。
なお、文例には掲載していませんが自動車も財産分与の対象です。
物理的に自動車を半分に切りわけることはできないので、
夫婦間の協議で2つの選択肢(一方が乗り続ける又は売却して現金化)から選びます。
ただし、自動車ローンが残っている場合、ローン会社の制約を受けるので専門家への相談をお勧めします。
また退職金や借金については離婚の時期や状況に応じて個別検討が必要です。これについても専門家への相談をお勧めします。
財産分与の分配割合はどうなる?
財産分与の分配割合は折半(50%)が公平だと考えられています。
ただご夫婦の離婚時の状況や離婚後の環境に応じて柔軟な結論を出すこともできます。
柔軟な結論とは折半以外の分配割合(7対3など)です。
詳細は財産分与の相場のポイントは3つをご覧下さい。
なお、文例2は甲が不動産を取得したので、預貯金は乙が9割(500万円の内450万円)受取るという結論を出しています。
子ども名義の財産の注意点
子どもの財産として子ども名義の預貯金が考えられます。
この預貯金は預金をした経緯に応じて財産分与の考え方が変わります。
〈預金をして経緯とは?〉
・子どもの将来のために積立をしていた。(財産分与の対象になる。)
・お年玉やお小遣いを貯めていた。(財産分与の対象にならない。)
このように財産分与の対象になる場合は協議が必要、対象にならない場合は協議不要(子ども固有の財産)となります。
なお、預貯金以外にも児童手当やジュニアNISAについて夫婦間協議を行うご依頼者様もいらっしゃいます。
![]()
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
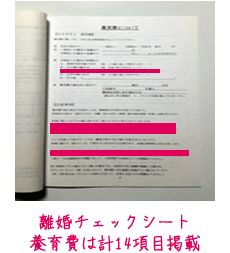
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
![]()
住宅ローンを完済しているご夫婦の選択肢は2つ

住宅ローンを完済している場合、銀行の制約を受けません。
つまり不動産の財産分与に関する夫婦間協議で揉める可能性は低く、主に2つの選択肢から結論を出します。
〈2つの選択肢とは?〉
A案 不動産を売却して現金を分配する。
B案 一方が不動産を取得する対価として他方に現金を支払う。
先ずA案は不動産を売却して売却益を分配します。
分配割合さえ合意できれば、夫婦間協議はスムーズに進みます。
例)売却益1000万円の内、夫が500万円、妻が500万円受取る。
ただし、不動産はすぐに売れるとは限らない(現金化まで時間がかかる)というデメリットがあります。
次にB案は一方が不動産を取得する代わりに他方へ現金を支払います。
具体的に支払う金額の合意ができれば、夫婦間協議はスムーズに進みます。
例)夫がマンションを取得する対価として妻に現金600万円支払う。
なお、B案は文例と書き方1と2に近い内容となります。
最後に参考情報としてB案を選択した場合に支払う金額の算出方法について解説します。
前提として支払う金額は夫婦間の協議で決めることになります。
その上で双方が公平だと納得しやすい支払う金額の算出方法は不動産屋さんに現在の価値を確認してその半値を支払う金額(マンションの価値が1200万円だから600万円を支払う。)にする方法です。
不動産屋さんは1社ではなく複数社に確認することをお勧めします。(相見積)
なお、B案で不動産の名義変更(夫から妻へ)が起きる場合、
法務局での登記が必要になるので司法書士さんへの相談、税金に関することは税理士さんへの相談をお勧めします。
以上のことから住宅ローンを完済しているご夫婦の場合、不動産を自由に扱うことができるので財産分与の協議はスムーズに進む可能性が高いです。
![]()
住宅ローンを返済中のご夫婦の選択肢は3つ

住宅ローンを返済中の場合、銀行からの制約を受けます。
つまり解決できる選択肢が少なく夫婦間協議が長引く可能性があります。
なお、ここでお伝えする3つの選択肢はあくまでも参考情報です。ご夫婦の状況によっては4つ目以降の選択肢が出てくる可能性が十分あり得ます。
〈3つの選択肢とは?〉
C案 不動産を売却する。
D案 住宅ローンを一括返済する。
E案 離婚後も一方が住み続ける。
先ずC案は不動産を売却することになります。
つまり売却額が住宅ローンの残高を上回っている必要があります。
例)売却額が900万円で住宅ローン残高が500万円。(アンダーローン)
ただ住宅ローンの残高が少ないケースを除いて、下回る(売却額が500万円で住宅ローン残高が800万円)ことが多いためC案を選択できるご夫婦は少ないです。
この下回る状況のことをオーバーローンと言います。
婚姻期間が短いご夫婦の場合、オーバーローンになる確率は高いです。
次にD案は住宅ローンの残高を繰上一括返済することになります。
一括返済できれば住宅ローンを完済しているご夫婦の選択肢は2つの状況に変わります。
ただ住宅ローンの残高が少ないケースを除いて、一括返済する現金を用意することが難しくD案を選択できるご夫婦は少ないです。
ここまでを整理すると選択肢C案とD案を選択できるご夫婦は少ないです。つまり解決できる選択肢とは言い難いです。
最後にE案は離婚後も一方が不動産に残って住み続けます。
不動産の名義人が住み続けて住宅ローンも支払っていくことになります。
例)夫名義のマンションに夫が残って住宅ローンも払っていく。
なお、E案では残る側の離婚後の支出を検討することが大事です。
〈なぜ検討することが必要?〉
夫「1人で生活を始めたけど広すぎる。」
夫「住宅ローンがあるので養育費の支払が厳しくなってきた。」
離婚することを考えて不動産を購入するご夫婦はいないです。
このことから離婚後にこのような状況になり養育費の支払に影響が出やすいです。
離婚後の養育費は子どもの成長に欠かせないお金です。
住宅ローンと養育費はリンクしないですが、トラブル防止のためにも離婚協議の段階から支出の検討をしてください。
不動産の名義を夫から妻に変更できる?
住宅ローンが残っている場合、夫婦間の合意だけで名義変更はできません。
銀行への相談と承諾が必要になるので夫から妻に名義変更することは難しいです。
銀行への承諾とはここでは住宅ローンの借換を指しています。
仮に妻に安定収入があり住宅ローンの借換が認められた場合は名義変更ができます。
住宅ローンの借換を検討される方は銀行への仮審査から始めて下さい。
なお、仮審査を通過した場合、銀行から不動産の財産分与の合意を記載した離婚協議書や離婚公正証書の提出が求められます。
このケースの流れとしては仮審査通過→離婚協議書又は離婚公正証書作成→離婚届提出→本審査通過→不動産の名義変更と住宅ローンの借換となります。(銀行ごとに異なる可能性があります。)
共有名義やペアローン(連帯債務)の場合は?
不動産購入の際、共働きのご夫婦だと単独名義(債務)ではなく共有名義にしたりペアローンを組んだというケースも多いです。(ペアローンではなく連帯債務のケースもあります。)
共有名義の場合、離婚後も現状維持(共有のまま)というご夫婦は少ないので、どちらかの単独名義にするという協議になりやすいです。(単独名義にする場合は住宅ローンの協議も必要です。)
このケースでは不動産の財産分与の難易度が一気に上がりご夫婦の状況や意向に応じて選択肢を考える必要があります。
様々な選択肢を考慮した上で結論を出すことが大事なので、依頼の有無は別として、1度は専門家に相談することが望ましいです。
![]()
家具家電など動産の財産分与が大事な理由

動産とは自宅にある家具家電(家財道具)のことです。
量(種類)が多く1つ1つ協議するのは面倒だと考えるご夫婦が多いです。
面倒だという理由で財産分与の分配協議を避けた場合、
離婚後、以下のようなトラブルに発展する可能性があります。
〈トラブルとは?〉
元妻「やっぱりテレビを譲ってほしい。」
元夫「テレビはいらないと言ったでしょ。今言われても困る。」
正直な話、テレビで揉める?と思う方もいるかもしれませんが、
新生活を始めた矢先に言われると、気分がいいものではありません。
注)元妻からの請求ではなく元夫から請求されるケースもあり得ます。
こういう訳で面倒だと考えても分配協議はして下さい。
ただ全ての家財道具について協議するのは大変なので以下の解決案があります。
〈A夫妻の財産分与の例〉
・夫はテレビと冷蔵庫を取得する。
・妻はエアコン、パソコン、プリンターを取得する。
動産の財産分与は例外を除いて自宅内の全ての家財道具が対象です。
全ての家財道具について分配協議を行うと時間と手間がかかるというデメリットがあります。
また離婚公正証書を作成する場合、財産リストだけでページ数が大量になり公証役場手数料が高くなります。
このデメリットを解消する方法はあります。以下の通りです。
〈デメリットを解消する方法とは?〉
A案 離婚後、返してと言われたら嫌なものに絞って協議する。
B案 高価なものや思い入れのあるものに絞って協議する。
A案やB案で分配協議をする場合、自宅内にある家財道具の量はかなり減らすことができます。上記A夫妻はB案(高価なもの)で分配協議をした例となります。
当事務所ではA案又はB案で分配協議をするご依頼者様が多いです。
なお、A案やB案以外の分配協議の方法はあります。
詳しく知りたいという方はお気軽に当事務所へご相談下さい。
![]()
理想的な財産分与の分配協議の進め方

財産分与の対象財産は不動産、預貯金、動産と種類が多いですが、1つ1つ丁寧に準備をすれば効率良く進めることができます。
〈理想的な分配協議の進め方とは?〉
① 現在の財産を確認する。
② メモ用紙に財産の一覧表を書き留める。
③ 財産分与と関係のない財産を確認する。
④ 誰が何を取得するという分配協議を行う。
⑤ 財産分与の最終合意。
先ず財産分与は婚姻中に蓄えた財産を清算(分配)します。
離婚を考えた時点で自宅にある①財産の確認から始めて下さい。
例)一軒家、自動車、預貯金、パソコン、掃除機など。
次に分配協議をスムーズに進めるためにメモ用紙を用意して①で確認した財産の②一覧表を作って下さい。一覧表は箇条書きで十分です。
なお、独身時代に購入したものや預貯金、相続財産は個人の財産なので財産分与の対象財産から除外されます。つまり③関係のない財産が②一覧表に含まれていないか確認をして下さい。
そして以下の流れで④誰が何を取得するかという分配協議を始めます。
〈財産分与の協議例1〉
夫「自宅と自動車はもらいたい。」
妻「その代わり預貯金、パソコン、生活家電がほしい。」
〈財産分与の協議例2〉
夫「自宅に残るから生活家電は1部譲ってほしい。」
妻「重い家電は譲るけど軽くて運べる家電はもらいたい。」
そして全ての財産の分配協議を終えれば⑤財産分与の最終合意となります。
財産分与の相場のポイントは3つ
① 夫婦間の協議で自由に決めれる
② 折半(50%)が公平で妥当
③ ご夫婦の状況に応じて柔軟に対応できる
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものです。
つまり財産分与の相場(分配割合)は①夫婦間で自由に決めることができます。
ただ財産分与は婚姻中に蓄えた財産を清算(分配)するものなので、一般的には②折半(50%)が公平で妥当だと考えられています。
なお、③離婚時のご夫婦の状況に応じて以下のように柔軟な結論を出すこともあり得ます。
〈どのような状況?〉
妻「子どもが3歳だから数年はフルタイムで働けない。」
夫「わかった。預貯金は折半ではなく3対7の分配でいいよ。」
子どもが幼い場合、離婚後、親権者はフルタイムで働くのが難しいです。
このことから離婚後の生活資金として預貯金を多めに分配するという結論を出すこともあり得ます。
上述の通り、協議離婚では双方が納得すれば相場を無視した条件合意をすることも可能です。
こういう訳で財産分与の相場は折半が基本ですが、ご夫婦の状況を考慮して柔軟に考えることもできます。