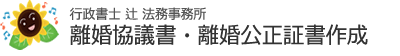離婚協議書や公正証書作成に伴う面会交流の疑問を解決

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 面会交流に関する5つの疑問をQ&A形式で回答
○ 面会交流を端的にまとめると
○ 面会交流の頻度は何回が妥当?
○ 頻度以外に決めるべき条件はある?
○ 面会交流の文例A案(頻度のみ決める)
○ 面会交流の文例B案(細かく決める)
面会交流は多くのご夫婦が話し合いを行い、離婚協議書や公正証書に記載することになる大事な離婚条件です。
ここでは面会交流に関する5つの疑問をQ&A形式でわかりやすい言葉を使って回答します。
![]()
面会交流に関する5つの疑問をQ&A形式で回答

離婚協議書や公正証書を作成する上で面会交流は大事な離婚条件となります。
ここではよくご依頼者様から頂戴する面会交流の5つの疑問をQ&A形式で回答します。
なお、面会交流をもっと知りたいという方は下記ページをご覧下さい。
・面会交流と公正証書の文例|面会交流の頻度や条件も解説
面会交流を端的にまとめると
離婚協議書や公正証書に記載する離婚条件の1つです。
具体的には離れて暮らす親と子どもとの離婚後の交流ルールを定めたものです。
面会交流は子どもの成長のために欠かせないものです。
夫婦間にわだかまりがあったとしても子どもの希望(気持ち)を優先して下さい。
なお、面会交流を養育費の取引材料にできません。
〈面会交流と養育費の取引材料(一例)〉
・養育費を0円にする代わりに面会交流は実施しない。
・養育費を増額してくれたら面会交流の回数を増やす。
このような条件は無効と判断されます。
つまり離婚協議書や公正証書に記載できないのでご注意下さい。
第三者のチェックを受けずにご夫婦だけで作成する場合、このような取引材料にした条件を記載していることが多いです。
面会交流の頻度は何回が妥当?
協議離婚は夫婦間協議で面会交流の条件を決めれます。
つまりご夫婦ごとに頻度(実施回数)が変わるので○回が妥当とは言えないです。
離れて暮らす親と子どもの関係性、離婚後の生活環境(居住地の距離など)、子どもの年齢(親権者同伴の必要性など)に応じて決めます。
なお、当事務所では月1~2回で合意されるご依頼者様が多いです。
ちなみに夫婦間協議の結果、頻度を決めないという結論もあり得ます。
例えば、離れて暮らす親と子どもの関係が良好な場合、あえて頻度を決めずに「子どもが望んだら実施(自由)」という抽象的な合意もできます。(夫婦間の関係が悪くても子どもとの関係は良好というケースも多いです。)
子どもが中学生、高校生の場合、自分の意思を明確に主張できるという理由から頻度ではなくこの結論を出すことが考えられます。
頻度以外に決めるべき条件はある?
親子関係に問題があったり、子どもが幼い場合、頻度以外に実施時間や面会場所など細かく決めるケースもあり得ます。細かく決めた結果、10個以上の条件になるご依頼者様もいます。
離婚後のトラブル防止のため養育費など離婚条件は細かく決めるべきですが、面会交流に限っては離婚時のご夫婦の状況に応じて細かく決めない方がよいケース(面会場所を公園と細かく決めたため雨の日の実施方法で揉めるなど)もあります。
つまり面会交流の条件はご夫婦ごとに抽象的(シンプルで少ない)、具体的(細かくて多い)、2つの方向性にわかれます。
最後に頻度以外に検討してもよい条件の一例を以下でお伝えします。
〈面会交流の条件(一例)〉
・面会以外のメールや電話などの交流に関する条件。
・夏休み、冬休みなどに実施する宿泊交流に関する条件。
・交流時にかかる費用負担に関する条件。
・中傷禁止(交流時に父母の悪口を言わない)に関する条件。
これらは検討してもよい条件(あくまでも選択肢)なので必ず決めないといけない。という訳ではありません。
面会交流の文例A案(頻度のみ決める)
乙は、甲が1か月の内1回、長女と面会交流することを認め、面会交流の日時や場所については面会交流の都度、協議の上決定する。
面会交流の文例A案は夫婦間のわだかまりや離れて暮らす親と子どもとの交流に抵抗感が少ない場合に決めることが多いです。離婚協議書や公正証書でよく見かける文例です。
文例A案の特徴は頻度(月1回)だけ決めておいてその他の条件(日時や場所など)は都度協議という抽象的な文例という点です。
文例の詳細解説は以下のページをご覧下さい。
・面会交流と公正証書の文例|面会交流の頻度や条件も解説
面会交流の文例B案(細かく決める)
甲及び乙は、甲と長女の面会交流について、1か月の内1回、毎月第1日曜日の午前9時から午後3時まで、実施することで合意した。
面会交流の文例B案は夫婦間のわだかまりや離れて暮らす親と子どもとの交流に抵抗感が多い場合に決めることが多いです。A案と同様に離婚協議書や公正証書でよく見かける文例です。
文例B案の特徴は離婚前に頻度や日時を決めておくという具体的な文例という点です。A案(抽象的)と比較すると違いがよくわかります。
なお、B案は頻度と日時だけ決めていますが、夫婦間協議の結果、待合せ場所や実施場所など更に具体的に決めることもあり得ます。この具体度はご夫婦ごとの状況により変わります。
文例の詳細解説は以下のページをご覧下さい。
・面会交流と公正証書の文例|面会交流の頻度や条件も解説
最後に頻度以外に決めるべき条件はある?で触れた通り、面会交流はご夫婦の状況により文例A案とB案の方向性にわかれます。どちらが正解、間違いという話ではないのでご注意下さい。
【参考情報】
・慰謝料協議の注意点や相場|離婚協議書や公正証書Q&A
・財産分与のやり方や話し合いのポイント|離婚協議書Q&A
・年金分割ってどんな離婚条件?|離婚協議書や公正証書Q&A
・通知義務ってどんな離婚条件?|離婚協議書や公正証書Q&A
・公証役場に行く前に知っておくべきこと|離婚公正証書Q&A